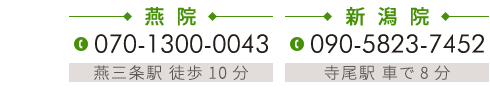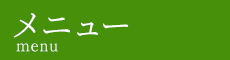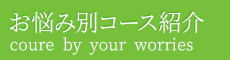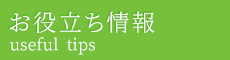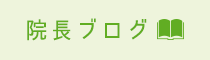こんにちは。
この前、スーパーを歩いていたら「リュックが開いているよ」って声かけて貰った、整体院晴々の今井です。その節は有難うございました。
さて、今日はそんな「人を助けることが、実は自分の脳にとって最強の栄養になるかも」ってお話です。しかも、ボランティアとか大層なことじゃなくてもOK。週に2〜4時間だけで、いいらしいんです。
結論:人助けは「脳トレ」より効くらしい(しかも長期的に)
アメリカ・テキサス大学オースティン校のHanさんたちが、なんと3万人以上(31,303人)の51歳以上の米国人を、22年間(1998〜2020年)追いかけて研究。
その結果——
✅ 他人を手助けしてる人は、認知機能の低下が緩やかだった
✅ しかもそれはボランティアでも、ただの友人サポートでもOK
✅ 継続してるほど、効果は積み重なる
✅ 必要な活動時間は週に2〜4時間だけ(多すぎると逆に疲れる?)
「ちょっとだけ」「たまに」じゃダメ? → いや、それでも効果アリ
Han氏いわく
「印象的だったのは、“短期的なスパイス”じゃなくて、“じわじわ効いてくる出汁”みたいに、年単位で効いてくるところ」
つまり、地味でもいいから続けることがカギ。
掃除手伝うでも、病院の送迎でも、お孫さんの面倒を見るでもいい。公式・非公式問わず、“人の役に立つ”という行動自体が、脳を守る力になるんです。
非公式な手助けも、ちゃんと効く。むしろ最強かも
ここがちょっと意外だったところ。
「え、ボランティアとか大げさなことしなくても、身近な人助けでもいいの?」
→ いいんです。それでも公式な活動に負けない効果が出てたそう。
「個人的な手助けは“社会的に評価されない”から、意味がないと思われがち。でも実際は、立派に脳に効いてた。これは嬉しい驚きでした」(Han氏)
なぜ「人助け」が効くのか?孤独とストレスの“抗体”になるから
研究チームの仮説では:
-
人助けは社会的つながりを強める
-
結果として孤立感や孤独感が減る
-
それが、認知機能低下のスピードを遅らせる
実際、活動を完全にやめてしまった人では認知機能の低下が加速する傾向もあったそうで、ここは要注意ポイント。
「誰かの役に立てる」って、やっぱり最強の薬
Hanさんの研究は、「人との関わり」が脳の老化にどれだけ強く作用するかを、データで証明してくれました。
しかもその関わりは、「公的な立場」である必要はない。「日常的な思いやり」でいいんです。
まとめ:人のこと手伝ってたら、なんか自分の脳も調子いい。
-
✅ 週2〜4時間の「人助け」が、脳の衰えをゆるやかにしてくれる
-
✅ ボランティアでも、家族の送迎でも、なんでもOK
-
✅ 続ければ続けるほど効果は大きくなる
-
✅ やめると、脳の衰えも進みやすくなる
-
✅ つまり、「他人の役に立ててうれしい」って感情は、脳にもご褒美
自分の負担のない範囲でできることをやって行きましょう!